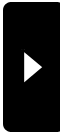2014年11月30日
宮口・六所神社の御祭神
浜北区宮口にある六所神社の御祭神は下記の様になっています。

底津綿津見神 中津綿津見神 上津綿津見神 底筒之男命 中筒之男命 上筒之男命
これらは海の神ですが、海から離れむしろ山地の南端にあたる宮口になぜ海の神が祭られているのか以前から気になっていました。
ところが最近読んだ浜松史跡調査顕彰会『遠江 十二号』の鈴木清市氏「「有玉伝説」と海人族」という記事にその謎を解き明かす記述がありました。
「確かな資料はないが、荒れ天竜にからんで海上の治安が田村麻呂東征の百年前から問題があった。例えば、七百拾八年に当時の実力者右大臣藤原不比等が勅を奉じて遠江海上鎮護の神として摂津国住吉神社に勧請して式内社津毛利神社を建設しているからである。」
「云うまでもないが、津毛利神社の津毛利族の族祖を祀る神社であって、遠州海上鎮護とは遠州灘や天竜川口を荒らす津毛利海人の海賊行為をもてあまし神人として社領を与へて懐柔したのである。」
つまり古代海上を荒していた津毛利海人族を懐柔するため津毛利神社を建てたということのようなのですが、この津毛利族は坂上田村麻呂に係わる有玉伝説にも関係しているらしいのです。
「「袖仕ケ浦由来の記」にも同様に天竜川を荒らす行為をあげ、問題化したことが述べられている。…赤蛇神は一度の渡海は認めるが二度三度の渡海は認めず転覆したというのである。」
「赤蛇神は船を転覆する人間のあだ名のようである。云うまでもないが、時代が進むに従って、通行人や輸送物資は増加し渡海は多忙となり、一日一度の渡海は二度、三度となる。本来は増船さる可きだが、船が自由にならぬ貴重な時代故、回数をふやした。だが、回数がふえれば渡海関係の労務者はひどい過労になり、不満となり、遂には船への妨害行為となった。それは、船が転覆し破船すれば休めるし、労働条件も改善されるだろうと考えたのだろう。勿論、このゴタゴタを利用して転覆の裏では川中での荷物の横奪があったと思う。彼等がねらうのは米穀其他の公私の物資であり、転覆させ海中で沈んだ荷物を横奪するのである。海人は潜水漁法で魚貝を採取するのが上手であったから、横奪は自在だったのである。」
有玉伝説では赤蛇が渡海を妨げたことになっていますが、これが渡船関係の海人族だったとすればがぜん現実味を帯びてきます。
「この地方の津毛利族は、この阿曇族の別れの末端の族であって、祭神は阿曇民族が祀る底津少童命、中津少童命、表津少童命と津守民族が祀る底筒男命、仲筒男命、表筒男命の六神であり、神社は摂津の住吉神社の分れである式内社津毛利神社であった。」
少童命(わたつみのみこと)は日本書紀の表記で、古事記では綿津見神(わたつみのかみ)と表記される同じ神です。
「津毛利神社は四十六所の総鎮守となっているが、その他にも分れとみられる半田、宮口、奥山、於呂(古代の神体紛失のため不明というが、渡海を生業とする郷であったから海人族とみられる)と各地にも及んでいることによって、この地方に占める古代社会の海人族の勢力が想像される。」
まとめるとこんな感じでしょうか。
津毛利神社 -> 祭神
↓
海人族 ↓
↓
有玉伝説 -> 宮口六所神社
古代の歴史は特に地方では残っている文献等が少なくよくわからないことが多いですが、仮説とは言えこれくらい点と点がつながってくれると非常に楽しいです。
これらは海の神ですが、海から離れむしろ山地の南端にあたる宮口になぜ海の神が祭られているのか以前から気になっていました。
ところが最近読んだ浜松史跡調査顕彰会『遠江 十二号』の鈴木清市氏「「有玉伝説」と海人族」という記事にその謎を解き明かす記述がありました。
「確かな資料はないが、荒れ天竜にからんで海上の治安が田村麻呂東征の百年前から問題があった。例えば、七百拾八年に当時の実力者右大臣藤原不比等が勅を奉じて遠江海上鎮護の神として摂津国住吉神社に勧請して式内社津毛利神社を建設しているからである。」
「云うまでもないが、津毛利神社の津毛利族の族祖を祀る神社であって、遠州海上鎮護とは遠州灘や天竜川口を荒らす津毛利海人の海賊行為をもてあまし神人として社領を与へて懐柔したのである。」
つまり古代海上を荒していた津毛利海人族を懐柔するため津毛利神社を建てたということのようなのですが、この津毛利族は坂上田村麻呂に係わる有玉伝説にも関係しているらしいのです。
「「袖仕ケ浦由来の記」にも同様に天竜川を荒らす行為をあげ、問題化したことが述べられている。…赤蛇神は一度の渡海は認めるが二度三度の渡海は認めず転覆したというのである。」
「赤蛇神は船を転覆する人間のあだ名のようである。云うまでもないが、時代が進むに従って、通行人や輸送物資は増加し渡海は多忙となり、一日一度の渡海は二度、三度となる。本来は増船さる可きだが、船が自由にならぬ貴重な時代故、回数をふやした。だが、回数がふえれば渡海関係の労務者はひどい過労になり、不満となり、遂には船への妨害行為となった。それは、船が転覆し破船すれば休めるし、労働条件も改善されるだろうと考えたのだろう。勿論、このゴタゴタを利用して転覆の裏では川中での荷物の横奪があったと思う。彼等がねらうのは米穀其他の公私の物資であり、転覆させ海中で沈んだ荷物を横奪するのである。海人は潜水漁法で魚貝を採取するのが上手であったから、横奪は自在だったのである。」
有玉伝説では赤蛇が渡海を妨げたことになっていますが、これが渡船関係の海人族だったとすればがぜん現実味を帯びてきます。
「この地方の津毛利族は、この阿曇族の別れの末端の族であって、祭神は阿曇民族が祀る底津少童命、中津少童命、表津少童命と津守民族が祀る底筒男命、仲筒男命、表筒男命の六神であり、神社は摂津の住吉神社の分れである式内社津毛利神社であった。」
少童命(わたつみのみこと)は日本書紀の表記で、古事記では綿津見神(わたつみのかみ)と表記される同じ神です。
「津毛利神社は四十六所の総鎮守となっているが、その他にも分れとみられる半田、宮口、奥山、於呂(古代の神体紛失のため不明というが、渡海を生業とする郷であったから海人族とみられる)と各地にも及んでいることによって、この地方に占める古代社会の海人族の勢力が想像される。」
まとめるとこんな感じでしょうか。
津毛利神社 -> 祭神
↓
海人族 ↓
↓
有玉伝説 -> 宮口六所神社
古代の歴史は特に地方では残っている文献等が少なくよくわからないことが多いですが、仮説とは言えこれくらい点と点がつながってくれると非常に楽しいです。