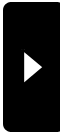2011年01月30日
遠州山辺の道の道筋(2)
遠州山辺の道の道筋は、どのくらい昔からあるのでしょうか。
『静岡縣史 第二巻』(昭和6年)には、気賀方面から都田川を溯り、都田から宮口に出て、於呂から天竜川の対岸野部に渡る道は最も古い東海道ではないか、というような記述があります。
また『郷土 浜北のあゆみ』(昭和53年)にも、「最近、学者の研究によると東海道が浜名湖の南を通るようになったのは六世紀ごろからであり、それまでは本坂越えを本道としていたという。」とあります。
東海道というと徳川家康が制定したいわゆる東海道五十三次が有名ですが、もともとの東海道は七世紀後半、飛鳥時代以降に五畿七道の一つとして整備されました。この古代東海道よりもさらに前の時代の幹線道が宮口・尾野・根堅辺りを通っていたのではないかというのです。
これらの本にはその根拠について直接の説明はありませんが、前後の流れから勝手に推測するに、どうやら昔はまだ海岸線が安定せず、また天竜川も暴れまわっていて歩き難かったので、浜名湖北岸の山沿いを通ったということのようです。
最新の学説がどうなっているのか気になるところですが、確かにこのエリアには六世紀頃の古墳が密集しており、いずれにしろその時代から交通の要衝であったことはたぶん間違いないのでしょう。

宮口土取の金刀比羅神社付近から東、宮口・於呂方面を望む。
左手前の山が高根山、正面の山は天竜川の対岸。
『静岡縣史 第二巻』(昭和6年)には、気賀方面から都田川を溯り、都田から宮口に出て、於呂から天竜川の対岸野部に渡る道は最も古い東海道ではないか、というような記述があります。
また『郷土 浜北のあゆみ』(昭和53年)にも、「最近、学者の研究によると東海道が浜名湖の南を通るようになったのは六世紀ごろからであり、それまでは本坂越えを本道としていたという。」とあります。
東海道というと徳川家康が制定したいわゆる東海道五十三次が有名ですが、もともとの東海道は七世紀後半、飛鳥時代以降に五畿七道の一つとして整備されました。この古代東海道よりもさらに前の時代の幹線道が宮口・尾野・根堅辺りを通っていたのではないかというのです。
これらの本にはその根拠について直接の説明はありませんが、前後の流れから勝手に推測するに、どうやら昔はまだ海岸線が安定せず、また天竜川も暴れまわっていて歩き難かったので、浜名湖北岸の山沿いを通ったということのようです。
最新の学説がどうなっているのか気になるところですが、確かにこのエリアには六世紀頃の古墳が密集しており、いずれにしろその時代から交通の要衝であったことはたぶん間違いないのでしょう。

宮口土取の金刀比羅神社付近から東、宮口・於呂方面を望む。
左手前の山が高根山、正面の山は天竜川の対岸。
この記事へのコメント
ごぶさたしておりました、にょろりです。
いいかげんなことは言ってはいけないと思い、いろいろ調べていたら、時間が経ってしまいました(^_^;)ゞ
本坂道(浜名湖の北を通る)ルートは、は山越えなので大変ですが、まるじゃがさんが推察するとおり、海岸沿いコースは海岸線が安定せず、気象条件にも影響されやすいという難点があります。状況によってどちらかのコースを使い分けていたとすると、本坂道がメインルートだった時期もあると思います。
本坂というのは湖西連峰本坂峠、愛知と静岡の県境の坂で、そこを通るから本坂道と言われているのですが、本坂から東ははどこを通っていたかと言うと、おそらく今の姫街道(細江-三方原台地-有玉あたりで台地を下り-磐田(遠江国府))ではないかと。姫街道の語源は古街道(ひねかいどう)という説もあるそうです。江戸時代には、姫街道は東海道の脇街道(サブルート)として利用されていたのはよく知られているところです。
では、宮口を通るルートはというと、姫街道の脇街道といったところでしょうか。今の道路に例えたら、国道362号線級・・・まったく例えになっていませんが・・・交通の要衝であることは間違いないです。古代は今のように道路がたくさんあったわけではないのですから、今の道路に比べてとても重要性は高かったと思います。
コメントが長くてすみません。調べていくうちに、他にもおもしろいことがたくさんありました(もっと長くなるので、とても書き込めませんが)。久々に遊ばせてもらいました。「大人の自由研究」って感じです。きっかけを作っていただいたまるじゃがさんに感謝しております。
いいかげんなことは言ってはいけないと思い、いろいろ調べていたら、時間が経ってしまいました(^_^;)ゞ
本坂道(浜名湖の北を通る)ルートは、は山越えなので大変ですが、まるじゃがさんが推察するとおり、海岸沿いコースは海岸線が安定せず、気象条件にも影響されやすいという難点があります。状況によってどちらかのコースを使い分けていたとすると、本坂道がメインルートだった時期もあると思います。
本坂というのは湖西連峰本坂峠、愛知と静岡の県境の坂で、そこを通るから本坂道と言われているのですが、本坂から東ははどこを通っていたかと言うと、おそらく今の姫街道(細江-三方原台地-有玉あたりで台地を下り-磐田(遠江国府))ではないかと。姫街道の語源は古街道(ひねかいどう)という説もあるそうです。江戸時代には、姫街道は東海道の脇街道(サブルート)として利用されていたのはよく知られているところです。
では、宮口を通るルートはというと、姫街道の脇街道といったところでしょうか。今の道路に例えたら、国道362号線級・・・まったく例えになっていませんが・・・交通の要衝であることは間違いないです。古代は今のように道路がたくさんあったわけではないのですから、今の道路に比べてとても重要性は高かったと思います。
コメントが長くてすみません。調べていくうちに、他にもおもしろいことがたくさんありました(もっと長くなるので、とても書き込めませんが)。久々に遊ばせてもらいました。「大人の自由研究」って感じです。きっかけを作っていただいたまるじゃがさんに感謝しております。
Posted by にょろり at 2011年02月14日 08:05
にょろりさん、ごぶさたです。
わたしの拙い文に対していろいろと調べていただきうれしい限りです。
実はわたしも自由研究感覚です。この地域のことに興味を持ったらいろいろと疑問が湧いてきて、それを調べるうちにどんどんつながっていくのがおもしろくってしょうがないのです。
ただ、つい想像(妄想?)がふくらみ過ぎる傾向がありますので、ぜひともツッコミをよろしくお願いします。
まだ不勉強でわたしもよくわかっていないのですが、「宮口を通る幹線道」というのは、律令時代よりも前の時代、つまりまだ磐田に遠江国府ができる前の話のようです。
その頃は今の袋井市の山梨あたりが栄えていたらしく、地図をみると宮口・於呂から対岸の野部・敷地を経て山梨に向かうのは自然に思えます。
次の記事では律令制以降の話をとりあげたいと思っています。
にょろりさんの「おもしろいこと」も、またぜひご披露ください。
わたしの拙い文に対していろいろと調べていただきうれしい限りです。
実はわたしも自由研究感覚です。この地域のことに興味を持ったらいろいろと疑問が湧いてきて、それを調べるうちにどんどんつながっていくのがおもしろくってしょうがないのです。
ただ、つい想像(妄想?)がふくらみ過ぎる傾向がありますので、ぜひともツッコミをよろしくお願いします。
まだ不勉強でわたしもよくわかっていないのですが、「宮口を通る幹線道」というのは、律令時代よりも前の時代、つまりまだ磐田に遠江国府ができる前の話のようです。
その頃は今の袋井市の山梨あたりが栄えていたらしく、地図をみると宮口・於呂から対岸の野部・敷地を経て山梨に向かうのは自然に思えます。
次の記事では律令制以降の話をとりあげたいと思っています。
にょろりさんの「おもしろいこと」も、またぜひご披露ください。
Posted by まるじゃが at 2011年02月15日 00:48
at 2011年02月15日 00:48
 at 2011年02月15日 00:48
at 2011年02月15日 00:48上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |